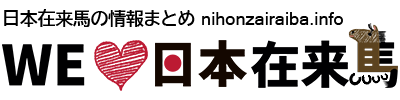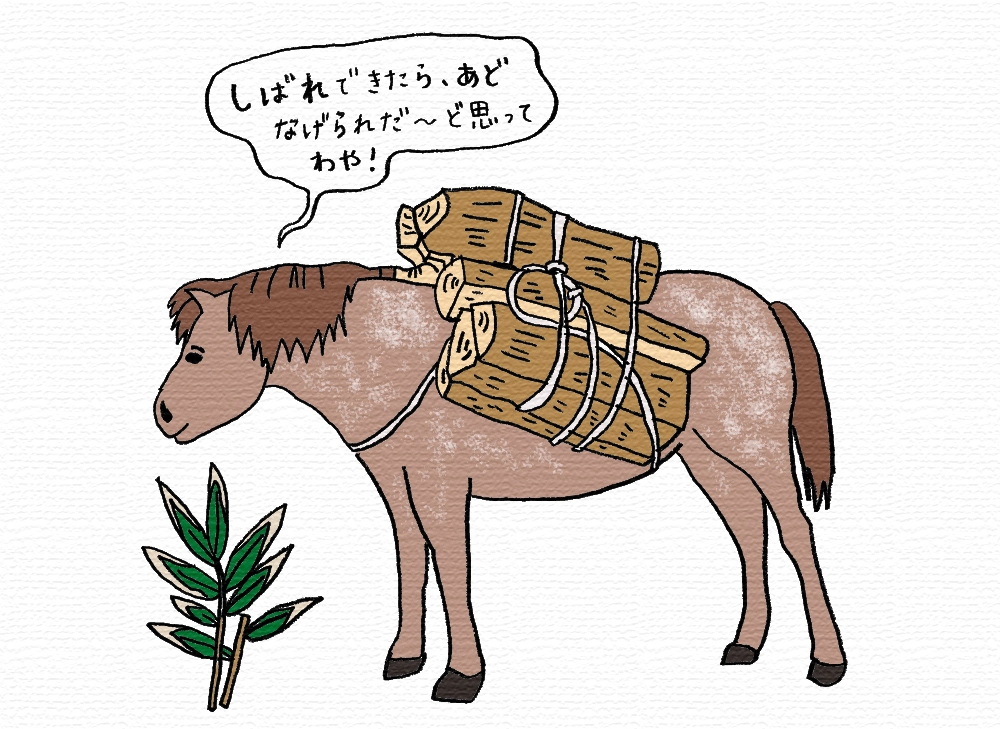
プロフィール
| 馬種名 | 北海道和種(別名:どさんこ、ドサンコ、道産子) |
| ふるさと | 北海道道南地域 |
| 体高 | 123~130cm |
| 体重 | 350~400kg |
| 飼育頭数 | 1,056頭(2024年,保存団体報告値) |
| 保護指定 | 北海道文化遺産(2004年) |
| 毛色 | 栗毛・栃栗毛・鹿毛・黒鹿毛・青鹿毛と、それぞれの粕毛。 芦毛、月毛、河原毛、佐目毛。 青毛とその粕毛もいるが、減少傾向。 鰻線のあるものもいる。 |
歴史と課題、そしてこれから
これまでのあゆみ
どさんこのご先祖様は、15世紀頃(江戸時代)に東北地方の有名な軍馬の産地だった南部藩の人々が、春になるとニシン漁や昆布漁の荷物を運ばせるために北海道南部に持ち込むようになった「南部馬」です。
秋になり、一緒に帰れるかと思いきや…なんと人間たちは、馬たちを置き去りにして行ってしまったのです。
残された馬たちは、北海道の厳しい冬を、雪の中に生えた「ミヤコザサ」を食べてたくましく生き延びました。
毎年新たな馬が連れて来られては置いて行かれを繰り返し、そのうち道央や道東地域へと暮らしの場を広げていきました。
2004年には「北海道の馬文化(ばん馬、日高のサラブレッド、北海道和種馬など)」として北海道文化遺産に指定されました。
ちなみにどさんこは、ばんえい競馬などで活躍する輓馬と混同されることも少なくないですが、あちらの先祖は体高180cm・体重1tにもなる外国産の大型馬で、全く別の種類のお馬さんです。
参考:Pacalla『ばん馬とどさんこ(北海道和種)のちがい』(2018年5月)
現在の取り組みと課題
人とコミュニケーションがとりやすい性格の馬が多いといわれており、現在は流鏑馬やトレッキングの乗用馬などのお仕事をしているどさんこが多いです。
乗り降りするにもちょうどよい高さで、体の幅が比較的広く、揺れの少ない側対歩ができる馬もいるので、乗馬をするタイプのホースセラピーには特に向いているといえるでしょう。※側対歩:同じ側の脚が同時に前に出る歩き方。競技用の乗馬では調教することで身に着けさせることもあるが、どさんこは遺伝的に自然にできる馬がいる。北海道では「じみち」ともいう。
側対歩の美しさを競う「じみち美人コンテスト」も保存団体主催で開催されています。
参考:ジョッパーズ『馬の歩き方、走り方の種類を学ぼう!』(2024年6月)
一方で、サラブレッド生産牧場の当て馬(メス馬の発情を確認するためのオス馬)にされたり、主に米軍基地向けの食用肉として利用されたりするものもいます。
馬好きとしてはネガティブな気持ちになりますが、経済動物としてそういった側面もあることは受け止めなくてはならない現実です。
現在どさんこはオス馬の数が減っているのに伴い、生産牧場の数も減少しています。
そのためこの先、遺伝子資源として家系の減少が危惧されます。
こうして年々頭数は減少しているものの、依然日本在来馬8品種の中では飼育頭数が最も多く、比較的ふれあう機会の得やすい馬種といえます。
そのため、悪いことではないのですが、北海道和種の保存に対してそこまで活発な動きが見られないという点が課題といえば課題かもしれません。
どさんこの普及啓発は全国の各施設にお任せといった感じで、保存会のホームページも長期間更新されていないようです。
これから期待される役割
伝統の流鏑馬行事や、競技としての流鏑馬大会でどさんこを活用しようとする動きが活発になっています。
どさんこのご先祖・南部馬のふるさとである青森県十和田市の「十和田乗馬倶楽部」では流鏑馬競技レッスンに力を入れており、桜の下で女性騎手が行う「桜流鏑馬」や「流鏑馬世界大会」など、馬を活用したイベント運営を行っています。
古来より伝わる流鏑馬をどさんこで行えば、日本古来の文化の保存とどさんこの保護活用が同時に叶いますので、今後もますます競技人口が増えていくことを願います。
また、新たなお仕事として、ミヤコザサの下草刈りを任せる取り組みが進められています。
機械で刈ると土ごと掘り返すことになって失われてしまう土の養分も、馬なら植物の部分だけを食べるので残ります。
さらにミヤコザサ以外の植物に対してもほどよい間引き効果があることがわかってきたため、馬本来の生態を利用して森林環境整備ができるのではないかと期待されています。
ちなみに周年放牧すると食べ過ぎてササが全滅してしまうので、このお仕事を任せられるのは冬季限定になります。
どさんこには「だんづけ」と呼ばれる伝統の荷物運搬技術があり、これを利用して「災害救助馬」として活躍させようという、社会貢献の道も模索されています。
災害時に孤立してしまった集落など自動車では行けないような険しい道でも馬なら入れるかもしれません。
負傷者や救援物資を運ぶ役割だけでなく、馬という生き物が行くことで被災者の心のケアにもなるのではないかと期待されています。
参考:NHKアーカイブス『どさんこ 北海道を“創った”馬』(2016年)
こちらは、だんづけの様子や、側対歩でぽこぽこ走るどさんこが動画で見られる貴重な資料です。ぜひご覧ください!
2025年3月15日(土)に行われた日本学術会議主催の公開シンポジウム「日本在来馬は、どこから来て、どこへ行くのか?」での講演によると、酪農学園大学の天野教授らは、環境適応力の高いどさんこのDNA情報を利用して牛などの家畜を丈夫にすることができないか?という研究を行っているそうです。
この研究によると、対象となったどさんこの多くに共通して、他の家畜にはない「自然免疫の強さを示すDNA」が検出されたとのことです。
これが他の家畜に応用できるようになれば、またどさんこの新たなお仕事が生まれるかもしれません。
またこの研究では、対象となったどさんこのうち半数の50%に共通して「側対歩ができるDNA」が見つかったそうですよ。
また、同シンポジウムにおいて『日本の馬』の編者である近藤誠司氏(北大名誉教授)が「馬好きの人には抵抗があるかもしれないが」と前置きしたうえで、どさんこを選別し食肉用として活用することを提言しました。
まず乗馬に適した体高140cm程度の中格馬、ホースセラピーに適したやや小柄でおとなしく仕事ができる馬を選抜して、側対歩ができるかできないかも明記します。
この選抜に合わなかった馬は積極的に食肉用として出荷し、得られたお金をまた保護活用の財源として使用するという循環を作るべきと考えている、とのことでした。
確かに馬好きとしてはざわざわする提言ではありますが、もっとも現実的な「馬がお金を産みだす仕組み」のひとつであることは間違いないでしょう。
保存団体情報
北海道和種馬保存協会
※公式サイトが長年更新されていないため、さっぽろまちづくり活動情報サポートサイトまちさぽの団体情報にリンクしています。
【本部】※道内8支部がそれぞれ独立予算で活動しています。
〒063-0804 札幌市西区二十四軒4条5丁目9-3 北海道獣医師会館3F
TEL:090-6269-7782 FAX:011-642-5521
E-mail:shirai-k@k4.dion.ne.jp![]()
![]()
動画で学ぶ
馬事文化財団 馬と人 在来馬を巡る8つの物語 北海道和種編
各在来馬が実際に暮らしている場所を取材し、飼養に関わる人たちのインタビューを中心に構成されています。
現場の空気感が伝わってくる資料映像です。
JRA日本中央競馬会 にっぽんの在来馬
リンク先で、日本在来馬についての紹介映像をご覧いただけます。
映像は2015年制作(各13分30秒)です。
映像ラインナップは以下の5本にまとめられています。
▶北海道和種馬 どさんこ
▶野間馬
▶宮古馬・与那国馬
▶木曽馬
▶対州馬・御崎馬・トカラ馬