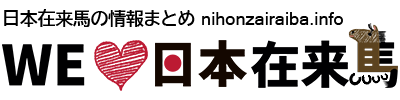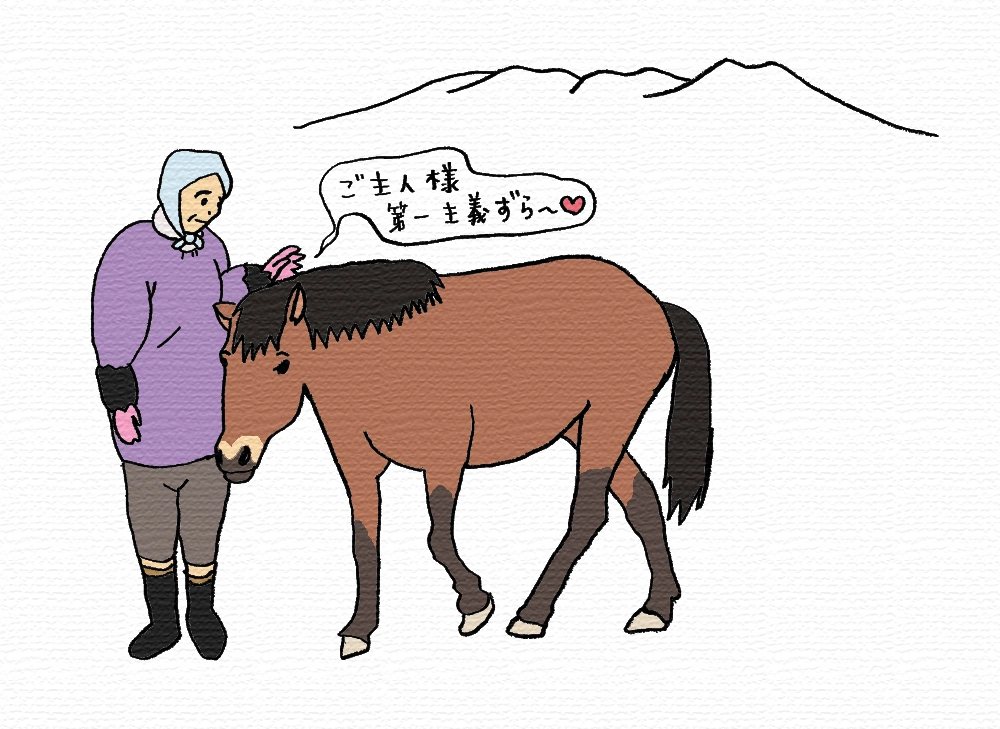
プロフィール
| 馬種名 | 木曽馬 |
| ふるさと | 長野県木曽地域(中部山岳地帯) |
| 体高 | 125~143cm |
| 体重 | 350~420kg |
| 飼育頭数 | 129頭(2024年,保存団体報告値) |
| 保護指定 | 長野県天然記念物(1983年) |
| 毛色 | 全体の85%が鹿毛。 栗毛、河原毛もいる。 鰻線がよく見られる。 |
歴史と課題、そしてこれから
これまでのあゆみ
6世紀頃(古墳時代〜飛鳥時代)にモンゴル在来馬の子孫が長野県木曽地域の中部山岳地帯に根付き、交通手段として、また米の代わりの上納品や自由売買による資金源として利用されるようになりました。
農家では木曽馬の仕事は専ら子馬の生産と堆肥作りだけ。
馬にきつい仕事をさせることはなかったそうです。
野良仕事や草刈りなどの重労働と馬の世話は女性の仕事で、「馬尊女卑」と言われるほど木曽馬は大事にされていました。
明治時代以降は飼育数の増減が激しくなり、大型の外国産馬や他地域の混血馬との交配を繰り返したため、純粋な木曽馬の特徴が失われる危機に陥ります。
戦後になって昭和天皇巡幸での木曽馬の天覧や上野動物園への寄贈によって木曽馬が話題になり、純血を復元しよう!という気運が高まりました。
一時は純血の木曽馬は絶滅したものとみられていましたが、長野県更埴市(現・千曲市)の武水別神社で「御神馬」として去勢を免れた純血の木曽馬が発見されます。
そのオス馬と、新開村で個人が飼育していた純血のメス馬を元に数を増やしたものが、現在の純血木曽馬とされています。
1983年には木曽郡内の優良馬を対象として長野県の天然記念物に指定されました。
現在の取り組みと課題
在来8種の中でも体格が大きいものが多く、体高がちょうどいい上に安定感があるので、ホーストレッキングなどの乗馬やホースセラピーで活躍している馬も多くいます。
また、子ども向けのふれあい体験や郷土学習にも利用されています。
馬の頭数を増やす・活用するだけでなく、木曽馬の保護活用に携わる「人を育てる」ことが重要だと考えてのことです。
木曽馬の里ではもっと木曽馬に親しみを持ってもらうためにトレーディングカードや缶バッジなど手作りのオリジナルグッズも販売し、これによって「馬が自らお金を産みだす」をも実現しようと取り組んでいます。
木曽馬を保護活用したいという人々の地道な活動により、行政もその取り組みに力を入れ始め「保存活用計画策定委員会」が開催されるようになりました。
128頭しかいないというわりには、意外と身近に木曽馬とふれあえる機会が多い気がする方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実は、純血ではないため馬事協会に登録はできない木曽馬系統の馬が全国各地で「木曽馬」として広く飼育されています。
混血を繰り返したことで体格にバリエーションができ、活躍できる用途の幅が広くなったという側面もありますので、それが一概に良くないことだとは言えません。
ただ、貴重な遺伝子資源を守るため「木曽馬らしさ」はこの先も保っていかなくてはなりません。
ですので「木曽馬の子孫」として木曽馬系統の馬も保護活用しつつ、純血の木曽馬を絶やさぬよう、注意深くバランスを取っていく必要がありそうです。
これまで帯広畜産大学で行ってきた受精卵移植による生産に木曽馬の里でもチャレンジをし始めたということですので、成功して純血の木曽馬を木曽の地で増やすことができるといいですね。
これから期待される役割
岐阜県の妻木八幡神社伝統の流鏑馬神事において、木曽馬を活用しようとする動きがあります。
流鏑馬神事は、地域に木曽馬がいなくなってから数十年は引退競走馬のサラブレッドで行われていました。
しかし、かつての祭りの姿を復活させたいという想いから江戸時代の衣装や道具を再現し、木曽馬の里の協力を得て木曽馬で流鏑馬神事を行うようになりました。
この流鏑馬行事に参加した子どもたちは木曽馬に親しみを持つようになり、のちに祭りの運営に携わることもあるそうです。
木曽馬が祭りに参加することで若者も祭りに関わる良い機会となっているとのことなので、今後も継続して木曽馬が活躍してくれることを願います。
比較的おだやかな性格ですが、気まぐれなところもあり、相手によっては言うことを聞かないことがあるといわれる木曽馬。
良く言えば“賢くて飼い主に従順”ということですから、日本犬の性質に通ずるところもあるような気がしますね。
きつい労働をさせない馬との暮らし方や、絶滅の危機からの奇跡の復活劇を知ると、木曽馬は本当に木曽に暮らす人々の深い愛情に支えられて生きてきたのだなあと思います。
全国に広く飼育されているということですから、純血かどうかにかかわらず「日本在来馬のことを知ってもらうための広告塔」になりうる存在といえるでしょう。
木曽馬は県内外でのイベント出張も多く、地域おこしのための観光資源としての活躍が期待されます。
青森県から山口県まで縦に長い本州でも唯一残る日本在来馬ということになりますから、これからはもっと多くの人々に深く愛される存在になっていってほしいですね。
保存団体情報
木曽馬保存会
〒397-0301 長野県木曽郡木曽町開田高原末川5596-1
木曽馬の里 木曽馬乗馬センター内
TEL:0264-42-3085 FAX:0264-42-3086
E-mail:kiso_uma@kis.janis.or.jp![]()
動画で学ぶ
馬事文化財団 馬と人 在来馬を巡る8つの物語 木曽馬編
各在来馬が実際に暮らしている場所を取材し、飼養に関わる人たちのインタビューを中心に構成されています。
現場の空気感が伝わってくる資料映像です。
JRA日本中央競馬会 にっぽんの在来馬
リンク先で、日本在来馬についての紹介映像をご覧いただけます。
映像は2015年制作(各13分30秒)です。
映像ラインナップは以下の5本にまとめられています。
▶北海道和種馬 どさんこ
▶野間馬
▶宮古馬・与那国馬
▶木曽馬
▶対州馬・御崎馬・トカラ馬