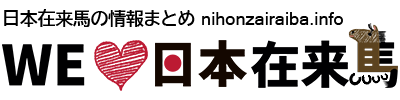プロフィール
| 馬種名 | 野間馬 |
| ふるさと | 愛媛県野間地方(現・今治市周辺) |
| 体高 | 90~120cm |
| 体重 | 約150kg |
| 飼育頭数 | 54頭(2024年,保存団体報告値) |
| 保護指定 | 今治市天然記念物(1988年) |
| 毛色 | 鹿毛、青毛、栗毛、芦毛。 鰻線のあるものが多い。 |
歴史と課題、そしてこれから
これまでのあゆみ
江戸時代、今治藩が軍馬を得るために農家に馬を飼育させたのが愛媛県野間地方の馬文化の始まりです。
比較的小さな馬は無償で農家に払い下げられ、農耕やみかんの収穫・運搬に活躍しました。
その馬たちが、のちに野間馬と呼ばれるようになりました。
みかん畑の急坂を行き来するには小さい馬の方が便利だったため、小さな馬同士で代を重ねるごとに小型化が進み、現存する在来馬8品種の中でもっとも体格の小さな品種となったのです。
体は小さいけれど力持ち!急な坂道だらけの果樹園を重たいみかん箱を背負って運ぶうちに、丈夫な体と蹄鉄が不要なほど固いひづめを手に入れました。
そんな野間馬もやはり農業の機械化が進むと急激に数を減らし、昭和30年代にはついに野間地域からすっかり姿を消してしまいます。
この状況に気づき、最初に野間馬の保存に取り組んだのは道後動物園(現・とべ動物園)でした。
1959(昭和34)年からは松山市に住んでいた長岡悟氏が「日本の伝統文化を守りたい」という思いから、周辺地域にわずか4頭残っていた野間馬をかき集めて飼育を始めました。
それを1978(昭和53)年に野間馬のふるさとである今治市に寄贈したことで、当時の「野間馬放牧場」へと里帰りを果たすことが叶ったのです。
これが現在の「のまうまハイランド」で、ほとんどの野間馬がここに集められて飼育されています。
1988年には、今治市の天然記念物に指定されました。
現在の取り組みと課題
週末になると家族連れでにぎわうのまうまハイランドでは、野間馬と子どもたちとのふれあいを大切にしています。
乗馬やブラッシングなど馬の世話をしたり、生まれた子馬に名前を付けたりといったクラブ活動や、職場体験の受け入れも行っています。
多くの子どもたちに乗馬を楽しんでもらいたいところではありますが、野間馬は体が小さく、さらに高齢の馬が多くなっており、乗馬ができる馬の数自体も減ってきているという事情があります。
馬の負担を考慮すると、乗る人の体重は25kgまでとし、1日に1頭の馬が乗せられる回数も制限せざるを得ない状況です。
また繁殖を終了した馬や去勢済みの馬、高齢の馬は特におとなしく、ホースセラピーにぴったりなのですが、現在は保存と繁殖に力を入れるためにセラピー活動はお休み中となっています。
繁殖の取り組みがなかなかうまくいかず、現在は岡山理科大の協力を仰いでいるところです。
研究者によると、馬が小さいため通常行うような検査ができないこともあり、生体観察をしながらできることを模索しているとのことです。
野間馬は、現在の繁殖用の馬集団だけでは先行きが不安なことから、繁殖・保存用のサブ集団を作る必要があるのではないかともいわれています。
さらに自然繁殖だけに頼るのではなく、凍結精子の作製や保存に関する研究を進め、ジーンバンクを確立することが重要な鍵になるとされています。
ただ、単に頭数を増やせばいいというわけではなく、実はのまうまハイランド内で飼育できる頭数に限界があることにも課題を抱えています。
のまうまハイランド内での飼育が80頭を超えた2004~2008年には闘争によるケガや死亡事故、疝痛による体調不良といった弊害が起きてしまいました。
これにより、この飼育場内では50~60頭を維持することが適切だということが明らかになったのです。
頭数を増やし、そして災害や疫病による全滅を避けるためには、他の地域に飼育場所を拡大する必要があります。
そのため保存会としては、今後も他の地域の動物園などへ譲渡や貸し出しを進めていく考えです。
これから期待される役割
地域に愛されるアイドルであり、子どもたちに命の大切さと地域の伝統文化を教えてくれる立派な先生である野間馬。
のまうまハイランドには「かつて親に連れられて遊びに来た」という思い出を語る人たちが、今度は自分の子どもを連れて遊びに来ています。
「乗り手の体重や乗馬回数を制限してもなお体験の提供を続けるのは、ここが親から子へと紡がれる思い出づくりの場所だから。」という言葉に、のまうまハイランドスタッフの強い思いを感じます。
毎年秋頃には「ちびっ子のまうま祭」というふれあいイベントが開催され、様々なステージパフォーマンスや屋台などが楽しめます。
乗馬体験のほか、選りすぐりの野間馬が障害飛越や台乗り、橋渡りなど技を披露するホースショーも行われます。
馬に農機具を牽かせる練習を応用した「ロングレーン」という調教方法で、馬がくわえているハミに2本の長いロープをつけ、後ろの方から馬を操作するドライビング体験も提供。
横に並んで歩く通常の引き馬や、乗馬とはまた違った馬とのコミュニケーションを体感することができます。
こうして野間馬をより多くの人に知ってもらおうと必死に取り組む人がいる一方、地域密着型の現状維持でいいじゃないかという考えの人も少なくないようで、あまり保護活用に力が入れられていない状況を心配する声も聞かれます。
せっかく小さくてかわいらしく素直な性格なのですから、積極的にセラピー活動にも従事できるよう、まずは飼育頭数が増えてくれることを願わずにはいられません。
保存団体情報
野間馬保存会
〒794-0082 愛媛県今治市阿方甲246-1
JAおちいまばり乃万支所内
TEL:0898-32-8155 FAX:0898-32-8255
動画で学ぶ
馬事文化財団 馬と人 在来馬を巡る8つの物語 野間馬編
各在来馬が実際に暮らしている場所を取材し、飼養に関わる人たちのインタビューを中心に構成されています。
現場の空気感が伝わってくる資料映像です。
JRA日本中央競馬会 にっぽんの在来馬
リンク先で、日本在来馬についての紹介映像をご覧いただけます。
映像は2015年制作(各13分30秒)です。
映像ラインナップは以下の5本にまとめられています。
▶北海道和種馬 どさんこ
▶野間馬
▶宮古馬・与那国馬
▶木曽馬
▶対州馬・御崎馬・トカラ馬