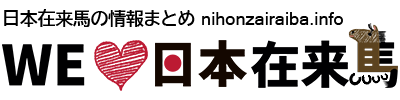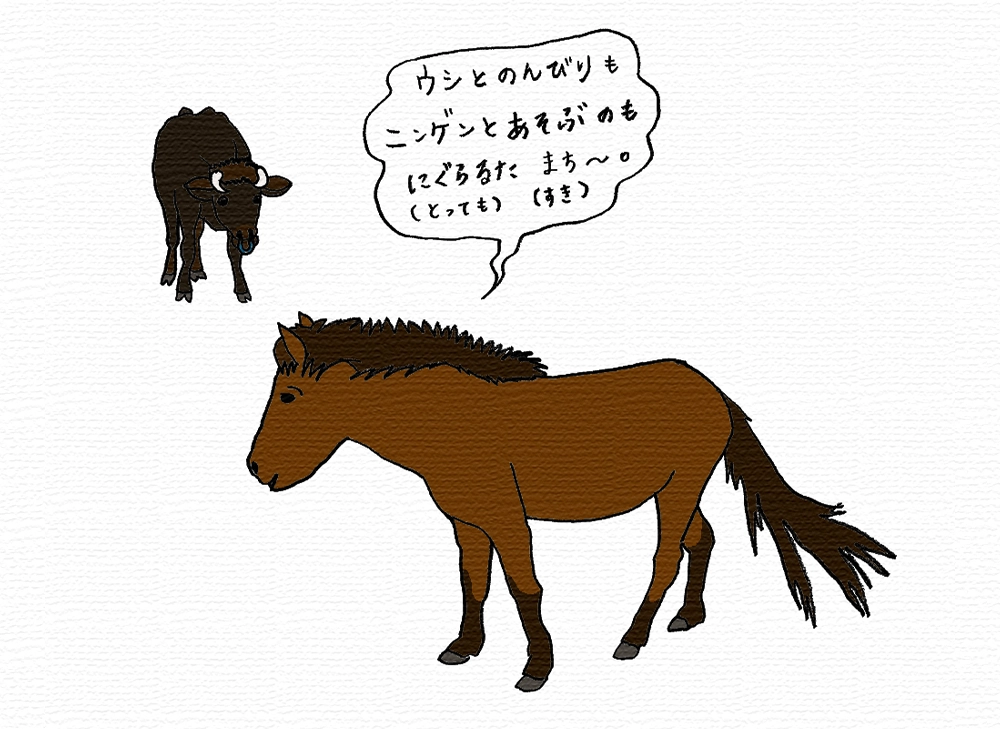
プロフィール
| 馬種名 | 与那国馬 |
| ふるさと | 沖縄県八重山諸島 日本最西端・与那国島 |
| 体高 | 110~120cm |
| 体重 | 200kg |
| 飼育頭数 | 89頭(2024年,保存団体報告値) |
| 保護指定 | 与那国町天然記念物(1969年) |
| 毛色 | ほぼ鹿毛。 日焼けのため判別が難しいものも多い。 昔の記録には粕毛、青毛、鹿毛、栗毛などあったが、 島では鹿毛が好まれた結果ではないかといわれている。 鰻線あり。 |
歴史と課題、そしてこれから
これまでのあゆみ
与那国島は、沖縄本島から南西へ約509km、石垣島から約127km離れた、日本最西端の離島です。
与那国馬は、少なくとも16世紀以降に琉球王府や石垣島、その他近隣諸国との交易によって与那国島へやってきたと考えられていますが、もっと南の方の島々が起源だとする説も否定されていません。
19世紀頃からは荷物の運搬や交通手段として利用されるようになりました。
この頃から牛と一緒に放牧されているのが、与那国馬の特徴のひとつです。
他の地域に比べて馬が普及した時期も遅く、人口が少なく、琉球王府からでさえも距離が遠くて統治しにくかった与那国島。
琉球競馬などの琉球支配層の馬事文化の影響は受けませんでしたが、その代わり、島独自の「浜競馬」が行われていたそうです。
浜競馬は稲に害虫がつかないように祈願するムヌン(物忌祭)の後に農業に関する話し合いをしながら、相撲などと共に楽しまれた娯楽です。
ほかの在来馬が激減する要因となった在来馬の去勢を命じる法律の影響は、与那国島には及びませんでした。
それでもやはり戦後の機械化の影響は大きく、1969年に与那国町天然記念物に指定、1970年代には飼育頭数が二十数頭まで減少したため保存会が結成されました。
そして1982(昭和57)年、絶滅の危機を伝える新聞記事に衝撃を受けた久野さんが神奈川県から与那国島に移住し、1992(平成4)年に「NPOヨナグニウマふれあい広場」(現・一般社団法人ヨナグニウマ保護活用協会)を開設。
これをきっかけに、与那国島と与那国馬に魅せられた若者が島に集まるようになり、保存活動が盛んになりました。
現在の取り組みと課題
ヨナグニウマ保護活用協会の本部は沖縄県南城市の「うみかぜホースファーム」にあり、与那国島の「ちまんま広場」、久米島の「久米島馬牧場」、石垣島の「石垣島馬広場」、静岡県の「伊豆の国うま広場」の5団体で構成されています。
日本在来馬の各保存団体の中でも、情報発信にかなり力を入れている印象です。
与那国馬は優しく素直な性格で、蹄鉄を履かずともサンゴ石灰岩の悪路をものともしない固いひづめを持っています。
その性質を利用したふれあい施設が島内外にあり、海馬遊び・ビーチライド・トレッキングなどのさまざまな「馬遊び」を提供しています。
主に夏季限定で体験できる海馬遊びは、馬に乗ったまま海に入ったり、尻尾につかまって泳いだりといった特別な体験ができます。※施設によって内容は異なります。
通常のハミではなく島伝統の木製馬具を使用した乗馬体験ができる施設もあり、普段とひと味違った馬との意思疎通を体感してみたい方にはこちらもオススメです。
琉球王府以来約300年間にわたり行われていたものの太平洋戦争によって中断された「琉球競馬ンマハラシー」を復活させようという動きもみられます。
競馬と言ってもスピード勝負ではなく、側対歩の脚運びの美しさや騎手と馬との一体感、衣装や飾りなどの優美さで勝敗が決まるのが特徴です。
沖縄本島にある「沖縄こどもの国」では2013年に約70年ぶりにンマハラシーを復活させ、離島も含めた県内各地から馬と人が集まるようになりました。
ヨナグニウマ保護活用協会も後援しており、毎年多くの与那国馬が参加しています。※与那国馬以外の交雑馬やポニーも参加します。
これは「うみかぜホースファーム」の中川さんの言葉です。
現代の馬は家畜という存在でしかないので、人が飼わなくなればそのまま死に絶えてしまう。ヨナグニウマを活用して「価値がある」「人間のために役立っている」ということを示しながら、彼らが必要とされる社会をつくっていきたい。
広く全国に与那国馬を譲渡して活用してもらおうとした時期もあったようですが、結局飼いきれなくなったり、個人のペットとして飼養されているだけだったりと、なかなか活用までは至らなかったとのこと。
ただ種を保存するだけではダメで、とにかく“活用”していかなくてはならないという危機感が「ヨナグニウマ保護活用協会」という団体名にも表れているのだと思います。
また、かつて農業や漁業に従事していた与那国馬ですので、その役割がなくなるにしたがい、与那国馬に携わる地元の人が減っています。
そのため、地元の人たちが与那国馬にあまり興味がないことも課題となっています。
北牧場・東牧場の中でケガをしてしまった馬や他で飼いきれなくなったりした馬の保護からスタートし、里親制度を運用している「NPO風馬与那国馬倶楽部」は、「ふれあえる馬を育てることも重要」と考えています。
小学校で乗馬の授業を行い、子どもたちがその成果を運動会で披露しています。
またナーマ浜で行われたカジキ釣り大会で乗馬体験会を開催し、ふれあいを通して地元の人に与那国馬を知ってもらおうという取り組みも行っています。
ふれあえる馬を育てるということは、活用の幅が広がることにもつながりますので、今後も継続して取り組まれることを望みます。
これから期待される役割
与那国空港の西隣に位置する北牧場(70ha)に約80頭、東崎灯台のある東牧場(60ha)に約15頭、人の手がほとんどかけられずに牛とともに周年放牧されている馬集団がいます。※一般道沿いの南牧場にいる馬集団は純血の与那国馬ではありません。
すべての馬が牧場組合員によって交配の管理をされてはいますが、それ以外のことは基本的には自然任せ。
「馬が存在していること」そのものによって草地生態系が保たれており、馬本来の生態が島の生物多様性を保つ役割を果たしているといえます。
島の自然を守り続けるためにも、人の手によって与那国馬の集団を維持し続けることが必要です。
そのほか施設で飼育されている与那国馬は、牧場遠足やふれあいを通じた動物介在教育、ホースセラピーなど活躍の場を広げつつあります。
与那国馬について学ぶ研修事業も行われるようになってきており、保護活用に関わる人材の育成も期待されます。
日本在来馬がどうやったらお金を稼げるようになるのか?
そのロールモデルを、与那国馬が示してくれるかもしれません。
保存団体情報
与那国馬保存会
〒907-1801 沖縄県八重山郡与那国町字与那国129
与那国町役場産業振興課
TEL:0980-87-3582 FAX:0980-87-3202
一般社団法人ヨナグニウマ保護活用協会
〒901-1412 沖縄県南城市佐敷新里1688
ユインチホテル南城うみかぜホースファーム内
TEL:090-6869-5788
E-mail:info@yonaguniuma.com![]()
Let’s support! ヨナグニウマ
〒272-0013 千葉県市川市高谷3-1285-1
日本パレット流通センター(株)
TEL:047-328-8010(栗城)![]()
![]()
![]()
動画で学ぶ
馬事文化財団 馬と人 在来馬を巡る8つの物語 与那国馬編
各在来馬が実際に暮らしている場所を取材し、飼養に関わる人たちのインタビューを中心に構成されています。
現場の空気感が伝わってくる資料映像です。
JRA日本中央競馬会 にっぽんの在来馬
リンク先で、日本在来馬についての紹介映像をご覧いただけます。
映像は2015年制作(各13分30秒)です。
映像ラインナップは以下の5本にまとめられています。
▶北海道和種馬 どさんこ
▶野間馬
▶宮古馬・与那国馬
▶木曽馬
▶対州馬・御崎馬・トカラ馬