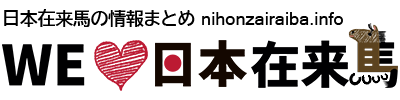プロフィール
| 馬種名 | 対州馬(別の読み:たいしゅううま) |
| ふるさと | 長崎県対馬市(対馬島) |
| 体高 | 125~135cm |
| 体重 | 200~300kg |
| 飼育頭数 | 44頭(2024年,保存団体報告値) |
| 保護指定 | 対馬市天然記念物(1979年) |
| 毛色 | 鹿毛、黒鹿毛が多い。 次いで栗毛が多く、 数頭のみ青毛、青鹿毛も。 鰻線のあるものもいる。 |
歴史と課題、そしてこれから
これまでのあゆみ
対州馬の先祖は朝鮮半島から渡来した説が有力ですが、詳細はわかっていません。
8世紀には聖武天皇に献上したという記録が残っており、朝鮮との交易品としても利用されたと考えられます。
江戸時代には島内に4ヶ所の牧場があり、東北地方の南部馬を繁殖用のオス馬として導入するなど馬産振興が行われていました。
当時の記録によると1904年には4,444頭の対州馬がいたそうです。
明治時代以降は他の在来馬の例にもれず外国産馬との混血が進み、純血性が問題視されるようになりました。
戦後になると農業用に使い勝手の良い小さな馬が好まれるようになり、島内の優良馬による「戻し交雑」に近い形で対州馬本来の特徴を回復したものとみられます。※戻し交雑:ある両親から生まれた仔馬を、その両親のいずれかまたはそれに近い系統の馬と交配させること。戻し交配とも。
対馬島は険しい山々とリアス海岸の島ですので、機械化が進んでも、山道が整備される前までは対州馬が交通手段として各家々になくてはならない存在でした。
絵や写真などの記録を見ると、主に女性が対州馬を扱うことが多かったようです。
港から揚げた物資や木炭の運搬、田畑の開墾や耕作・堆肥作りにも活躍し、坂道を上る能力に優れ、蹄鉄が不要なほど固いひづめとたくましい脚を持ちながら、優しく親しみやすい性格も身につけていきました。
狭い坂道の上に家を建てるため、長崎市内の街づくりにおいても活躍したそうです。
一方、福岡県大牟田市の三井炭鉱で酷使され、平均2歳10ヶ月という短い一生を炭坑内で終えた対州馬たちが昭和の初め頃までいたということも忘れてはならない事実です。
1979年に対馬市の天然記念物に指定されました。
現在の取り組みと課題
近年では島民でも対州馬になじみのある人が減っており、対州馬展を開催した際のアンケートでも「馬がいるのはなんとなく知っていたが歴史については知らなかった」という回答が多かったとのこと。
そこで保存会では、イベントを通じて改めて島民に対州馬への親しみを持ってもらおうと取り組んでいます。
また小学校で出張授業を行ったり、キッズライダーを育成したりと、子どもたちに向けてふれあい体験を通じた郷土教育を行っています。
瀬田という地区では、1971年まで「初午祭」という子どもの厄払いと節句のお祝いを起源とするお祭りが行われており、余興として、対州馬の2頭立てのレースである「馬跳ばせ」がありました。
長らく途絶えていましたが、目保呂ダム馬事公園で2002年から初午祭を元にしたイベントが復活しました。
伝統の「馬跳ばせ」や「子ども相撲」のほか、6頭立てで勝ち馬投票や賞品もある「対馬ダービー」、乗馬体験、軽乗(走る馬の上でのパフォーマンス)、流鏑馬、障害飛越など、盛りだくさんのイベントになっています。
対州馬はの頭数は依然として絶滅寸前の水準で推移しており、保存団体では、島内外で140頭まで増やすことを目標としています。
遺伝子研究により、今いる46頭の対州馬の先祖を辿ると、たった26頭から始まった集団であることがわかりました。
近親交配を避けるためには正確な血統登録が重要とされ、現在は、サラブレッドのように親子関係をはっきり記録するための遺伝子調査が行われているそうです。
また現在ほとんどが鹿毛や黒鹿毛となっている毛色も、1929年には青毛が最多だったという記録が残っており、毛色に関わる遺伝子から今後も青毛を保存していくことができないか?という研究も進められています。
島内には目保呂ダム馬事公園に20頭・あそうベイパークに10頭・東横インに10頭に加え2ヶ所の繁殖牧場がありますが、島内だけでは飼育面積や人手にも限界があります。
頭数を増やし、また災害や疫病などでの全滅を避けるため、島外へ飼育場所を広げなければなりません。
遺伝的な特徴を維持しながら島外で頭数を増やすには、より多くの人々の対州馬に関する理解が必要ですので、島外の地域との結びつきを大切にしていくことが重要な課題となっています。
専門性を持った外部人材にも保存活動に参加してもらうため、保存会では情報発信にも力を入れています。
これから期待される役割
豊かな自然と歴史ある対馬島において、対州馬は観光資源として大いに期待されています。
エコツーリズムとして、島内の自然・文化遺産をめぐるホーストレッキングツアーを企画する動きもあるようです。
また馬糞堆肥を使ったブランド農産物の販売など、技術としては昔ながらのものでも、現代に合った新たな付加価値を付けて売り出そうという提案もされているとのこと。
対州馬保存会はSNSも積極的に活用しており、対州馬たちのかわいらしい姿がたくさん見られます。
世界中に癒しを届ける存在として広まってくれたら、今度はそれが巡り巡って対州馬の保護活用につながる可能性もあるのではないでしょうか。
一見まわり道に思えるかもしれませんが、日本在来馬保護活用における情報発信の大切さを示してくれる道しるべとなってくれるような気がします。
保存団体情報
対州馬保存会
〒817-0013 長崎県対馬市上県町佐須奈甲567-3
対馬市上県行政サービスセンター内
TEL:0920-84-2311 FAX:0920-84-2310
E-mail:taishuhorses@gmail.com![]()
![]()
![]()
![]()
動画で学ぶ
馬事文化財団 馬と人 在来馬を巡る8つの物語 対州馬編
各在来馬が実際に暮らしている場所を取材し、飼養に関わる人たちのインタビューを中心に構成されています。
現場の空気感が伝わってくる資料映像です。
JRA日本中央競馬会 にっぽんの在来馬
リンク先で、日本在来馬についての紹介映像をご覧いただけます。
映像は2015年制作(各13分30秒)です。
映像ラインナップは以下の5本にまとめられています。
▶北海道和種馬 どさんこ
▶野間馬
▶宮古馬・与那国馬
▶木曽馬
▶対州馬・御崎馬・トカラ馬