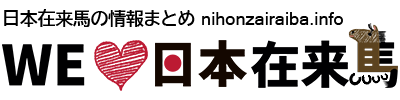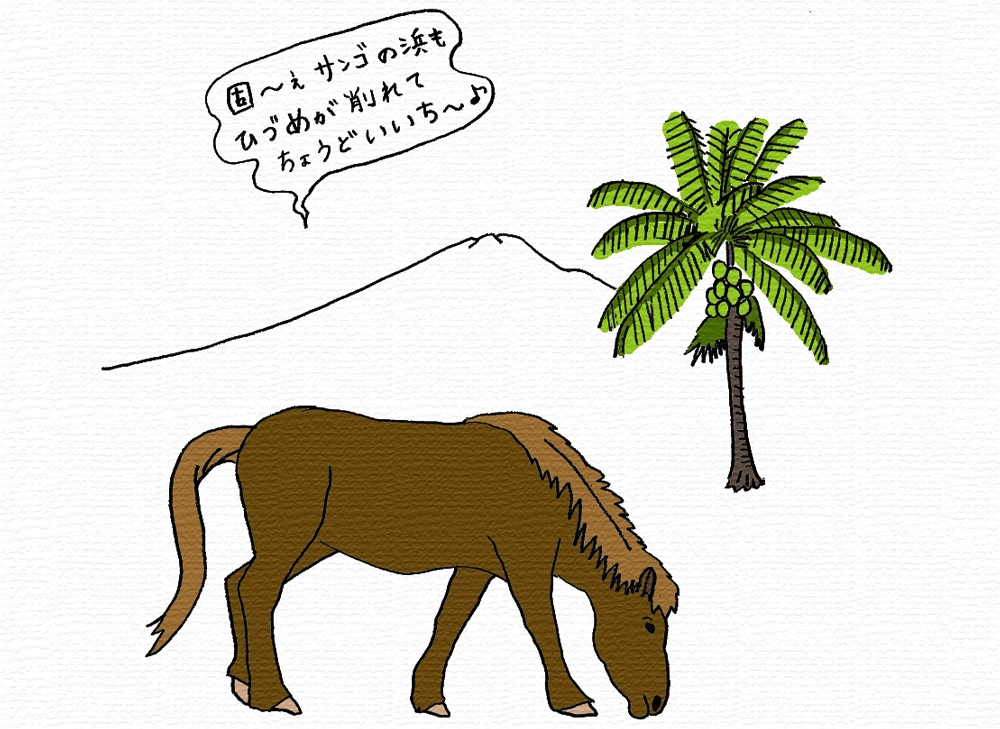
プロフィール
| 馬種名 | トカラ馬 |
| ふるさと | 鹿児島県鹿児島郡十島村(トカラ列島) |
| 体高 | 110~120cm |
| 体重 | 約190kg |
| 飼育頭数 | 92頭(2024年,保存団体報告値) |
| 保護指定 | 鹿児島県天然記念物(1953年) |
| 毛色 | 黒鹿毛、栃栗毛。 毛色を判別しにくい馬も多い。 首・肩に黒斑のあるものが10%程度。 ハッキリしないが、鰻線のあるものもいる。 |
歴史と課題、そしてこれから
これまでのあゆみ
トカラ列島は、屋久島と奄美大島の間の南北約160kmに点在する12島から成ります。
そのうち7島が有人島、5島が無人島です。
その中でトカラ馬が最初に認知されたのは有人島の「宝島」、現在主にトカラ馬が飼育されているのが有人島の中ではもっとも面積が広く人口が一番多い「中之島」となっています。
明治30年頃、奄美群島の東に位置する「喜界島」から未改良の在来種馬が宝島に導入されたのがトカラ馬の始まりという説が有力です。
荷物の運搬や農耕、サトウキビの栽培や砂糖の製造で活躍し、島民にとっては家族同然の存在として暮らしていました。
またトカラ列島には旧暦11月から12月にオヤダマ(先祖の魂)を迎え祝福する「七島正月」という独特の民俗行事があり、雪に見立てた砂を庭に敷いて門松を立てます。
その砂を海岸から運ぶのにも、トカラ馬が活躍していたそうです。
南の島でひっそりと暮らしてきた彼らですが、鹿児島大学の林田教授らが調査に入り、1952(昭和27)年に「トカラ馬」と命名したことで世に知られます。
翌1953年には鹿児島県の天然記念物に指定され、保存活動が始まりました。
その後やはり機械化が進むにつれ飼育頭数が減り、1963(昭和38)年には残り二十数頭にまでなってしまいました。
宝島での保護が困難と判断されたトカラ馬。
鹿児島の実業家であった岩崎與八郎氏の「トカラ馬を保護し、観光資源として活用したい」という申し出を受け、14頭が鹿児島県本土の開聞山麓自然公園に移されました。
昭和43(1968)年には鹿児島大学附属の入来牧場で、鹿児島市内の公園で飼われていたトカラ馬の放牧がスタート。
昭和48(1973)年に保存会が結成されました。
昭和50年代になり、トカラ馬をふるさとへ帰そう!ということで、鹿児島本土の4頭と宝島に1頭だけ残っていたオス馬を合わせて、全部で5頭がトカラ列島・中之島の牧場に移されました。
ところが、順調に増頭していた矢先、1994(平成6)年の大雨による水没で寄生虫被害が発生。
猛暑も重なり、約半数が死亡してしまいます。
保存会は急遽別の放牧地を作り、鹿児島本土から新たにメス馬2頭を導入することで、なんとかピンチを乗り越えました。
現在の取り組みと課題
元々島で人々とともに家族同然に暮らしていた頃のトカラ馬は、たいへん優しく素直な性格でした。
ところが、飼育頭数を回復するために放牧によって代を重ねるうち、その性格は失われてしまっていました。
せっかく頭数が増えても、人に馴れていなければ活用するのは難しく、保存に対する理解も得にくくなります。
そこで立ち上がったのが公益社団法人全国乗馬倶楽部振興協会の藤田知己氏でした。
その尽力により乗馬クラブなどの飼養現場に協力を得て調教が行われ、トカラ馬は人との絆を取り戻すことができたのです。
中之島の群だけで繁殖・増頭していくことには血が濃くなりすぎることによる弊害が伴うため、限界があります。
そこで、繁殖用の馬が必要になった時にはいつでも本土から送れるように、開聞山麓では管理に努めているとのことです。
鹿児島大学の入来牧場でも、トカラ馬の研究が継続して行われています。
中之島に鹿児島大学の獣医師が訪れ、遺伝子検査や伝染病の予防接種を行う動きも見られるようになりました。
今後も、いかに島と本土との連携を継続していくかが大きな鍵となっていくことでしょう。
これから期待される役割
現在トカラ馬は、ふれあいや乗馬体験などの観光資源として、また地元の子どもたちに対する教育活動や、セラピーホースとしても活躍しています。
中之島でも開聞山麓でも、訪れる人々にはできるだけトカラ馬にふれあってもらうことでもっと知ってもらいたいと、管理されている方は語ります。
中之島のトカラ馬牧場では一見自由に放牧されているように見えますが、18頭(2023年現在)の馬すべてにいっとう一頭名前がついていて、5代目となる管理人さんにかわいがられています。
子馬が生まれると新聞で名前を募集するなど、地元の人にも親しみを持ってもらえるよう取り組まれています。
現在トカラ馬のほとんどが黒鹿毛となっていますが、開聞山麓自然公園では久しぶりに栗毛の子馬が生まれたそうで、この調子で栗毛のトカラ馬も増やしたいとのことです。
遺伝的なバリエーションが増え、
トカラ列島には、鹿児島港から週2便出航する村営定期船「フェリーとしま」か、奄美大島の名瀬港から週1便未明に出航するフェリーに乗るしかありません。
遠方から向かう場合は、前後の宿泊手配も必要です。
悪天候による大幅な遅れや欠航の可能性もありますので、旅としてはなかなか難易度の高いものとなります。
また各島にタクシーやレンタカーはなく、移動は民宿を拠点に徒歩か島民のご厚意に甘えるしかありません。
確かに、わざわざ島へ行かずとも、トカラ馬に会える施設はあります。
ただ、開門山麓でトカラ馬の管理をされている方の言葉によれば「本土はあくまでも繁殖のためのサブ施設」。
島独自の文化の中で人々と共に暮らすトカラ馬の本質を全身で感じられるという意味では、苦労してでも島に渡る価値は十分あるのではないでしょうか。
中之島のトカラ馬牧場の正面には「十島村歴史民俗資料館」があります。
こちらと併設されている天文台も含めてすべてトカラ馬牧場と同じ方が管理されており、トカラ列島の人々が紡いできた歴史と文化を解説してくれます。
エコツーリズムのトカラ列島として、トカラ馬がそのアイコンになってくれることを期待します。
保存団体情報
トカラ馬保存会
〒890-0065 鹿児島市郡元1-21-24
鹿児島大学内
TEL:099-285-8589
動画で学ぶ
馬事文化財団 馬と人 在来馬を巡る8つの物語 トカラ馬編
各在来馬が実際に暮らしている場所を取材し、飼養に関わる人たちのインタビューを中心に構成されています。
現場の空気感が伝わってくる資料映像です。
JRA日本中央競馬会 にっぽんの在来馬
リンク先で、日本在来馬についての紹介映像をご覧いただけます。
映像は2015年制作(各13分30秒)です。
映像ラインナップは以下の5本にまとめられています。
▶北海道和種馬 どさんこ
▶野間馬
▶宮古馬・与那国馬
▶木曽馬
▶対州馬・御崎馬・トカラ馬